どうも!おはこんばんにちわ!
最近、完全にハマってしまったものがあります。それが、大相撲。
きっかけは、たまたまYouTubeで見かけた「二子山部屋のチャンネル」。稽古の様子や弟子たちの素顔、親方の厳しくも温かい指導を見ているうちに、「あれ?相撲ってめっちゃ奥深いじゃん…」って気づいて、気づけば深夜に動画をずっと見ちゃうほどになってました(笑)。
でも、見てるうちにふと疑問が…。
「幕内とか十両とかってよく聞くけど、実際どういう違いがあるんだろう?」
そこで今回は、僕みたいな初心者でもわかりやすく、大相撲の“番付”制度=階級の仕組みについてじっくり紹介していきます!
そもそも「番付」ってなに?【相撲界のランキング表】
大相撲には、力士たちの強さや成績によって決まる「番付(ばんづけ)」という制度があります。これは簡単に言えば、相撲界のランキング表。
番付は年6回、本場所のたびに更新され、勝ち越せば昇格、負け越せば降格というシビアな世界です。
まさに力士たちの“人生そのもの”が反映された表ともいえるわけですね。
【階級その①】幕内(まくうち)— 大相撲の最高峰!
僕が最初に覚えた階級がこの「幕内」。
テレビ中継でよく見るのがこの幕内の力士たちで、大相撲の花形・トップランクです。取組の迫力やオーラ、品格も段違いで、ここに上がるだけでも相当すごいこと。
幕内にはさらに5つのランクが!
- 横綱(よこづな):言わずと知れた最強の証。連敗したら引退が暗黙のルール。責任も重い。
- 大関(おおぜき):横綱に次ぐ地位。成績次第で降格もあるから気が抜けない。
- 関脇(せきわけ):実力者揃い。大関昇進を狙う注目ポジション。
- 小結(こむすび):上位常連を倒せば一気に出世も狙える。
- 前頭(まえがしら):一番人数が多く、若手からベテランまで混ざる層。
実体験:二子山部屋の取組で初めて“幕内の重み”を感じた
YouTubeの二子山部屋で、元幕内力士の稽古動画を見たとき、他の若手とは圧倒的な動きのキレ・間合いの取り方が違うんです。幕内って単に強いだけじゃなくて、“魅せる力”も必要なんだと感じました。
【階級その②】十両(じゅうりょう)— ここから“関取”!
十両に昇進すると、力士は**「関取(せきとり)」**と呼ばれ、プロの証ともいえる待遇を受けられるようになります。
関取になると、こんなに変わる!
- 月給制に! → 幕下までは無給ですが、十両からはちゃんと給料が出ます
- 化粧まわしの着用 → 幕内と同じく豪華な姿で土俵入り
- 付き人がつく → 身の回りの世話をしてくれる弟弟子ができる
この十両に昇進できるのはわずか28人(東西14人ずつ)。かなりの狭き門です。
実体験:関取の“別格感”に圧倒された話
ある日、二子山部屋の動画で十両力士が新弟子と一緒に稽古してるシーンを見たんですが、その威厳というかオーラがまるで違う。受けの力も全然違うし、「この人たちは本当にプロなんだ」って感じました。
【階級その③】幕下(まくした)— 関取を目指す登竜門!
幕下は、十両を目指す実力派力士たちが集まる層。1場所7番の取組で、好成績を収めると一気に十両入りが見えてくる!
ただし、ここにいる力士たちのレベルもめちゃくちゃ高い。すでに相撲歴10年超えとか、学生横綱経験者も普通にいます。
幕下の特徴まとめ
- 7戦制(勝ち越しで昇格のチャンス)
- 十両経験者もいる
- まだ給料はもらえない
稽古でも、幕下力士が弟弟子をビシバシ鍛える姿が見られて、「上下関係がリアルだな」と感じる層です。
【階級その④】三段目(さんだんめ)— 実力もキャリアもバラバラ!
三段目は、中堅クラスともいえる階級で、若手とベテランが混ざり合うカオスな階層。力士によって体格や経験がバラバラなので、毎場所なにが起こるかわかりません。
YouTubeで見ていても、三段目力士が思い切った攻めをして逆転勝ちする場面が多くて、意外と見ごたえあります。
【階級その⑤】序二段(じょにだん)— 若手と“おじさん力士”の混在層
序二段は、新弟子としてデビューして数場所目の若手と、ケガなどで番付を下げてきたベテランが混在する、なかなか面白い階級です。
負けが続くとすぐ降格する世界なので、「序二段に残る」だけでも結構すごい。
YouTubeのコメント欄でも、「この力士、昔は幕下だったのに…」みたいな話があって、相撲人生の浮き沈みを感じる層でもあります。
【階級その⑥】序ノ口(じょのくち)— すべての力士のスタート地点!
ここがすべての始まり。相撲界に入門して、「新弟子検査」をクリアすると、この序ノ口から番付がスタートします。
全勝(7戦全勝)すると、一気に序二段上位まで昇格することもあるので、ここは未来のスター発掘枠でもあります!
二子山部屋の動画では、序ノ口力士のデビュー戦に密着している回もあって、「この子が将来の関取になるかもしれない」というドラマ性がたまりませんでした。
番付の昇降はどう決まる?【勝ち越しか負け越しか】
大相撲では、毎場所の成績によって番付が変動します。
- 幕内・十両:15番の取組で勝ち越せば昇格、負け越せば降格
- 幕下以下:7番制で4勝以上が勝ち越しライン
特に幕下から十両、十両から幕内への昇進はドラマチックで、まるで就活の最終面接を勝ち抜くかのような緊張感があります。
まとめ|「番付」を知ると、大相撲は10倍楽しくなる!
- 大相撲の番付は全部で6つ(幕内・十両・幕下・三段目・序二段・序ノ口)
- 幕内のさらに上位には横綱・大関・関脇などのランクがある
- 十両からは“関取”として待遇が一変
- 番付は毎場所の勝敗で変動!まさに力士の人生そのもの!
僕のように「YouTubeきっかけ」で大相撲に興味を持った人でも、番付の仕組みを知るだけで、相撲観戦の楽しみ方がガラッと変わります!
次に観るときは、推し力士の階級や、どこを目指してるのかにも注目してみてくださいね!
ご意見や推し力士についてのコメントも大歓迎です!
二子山部屋のYouTubeはこちらから→二子山部屋 sumo food – YouTube
ではまた次の記事でお会いしましょう!
お問い合わせはこちらから

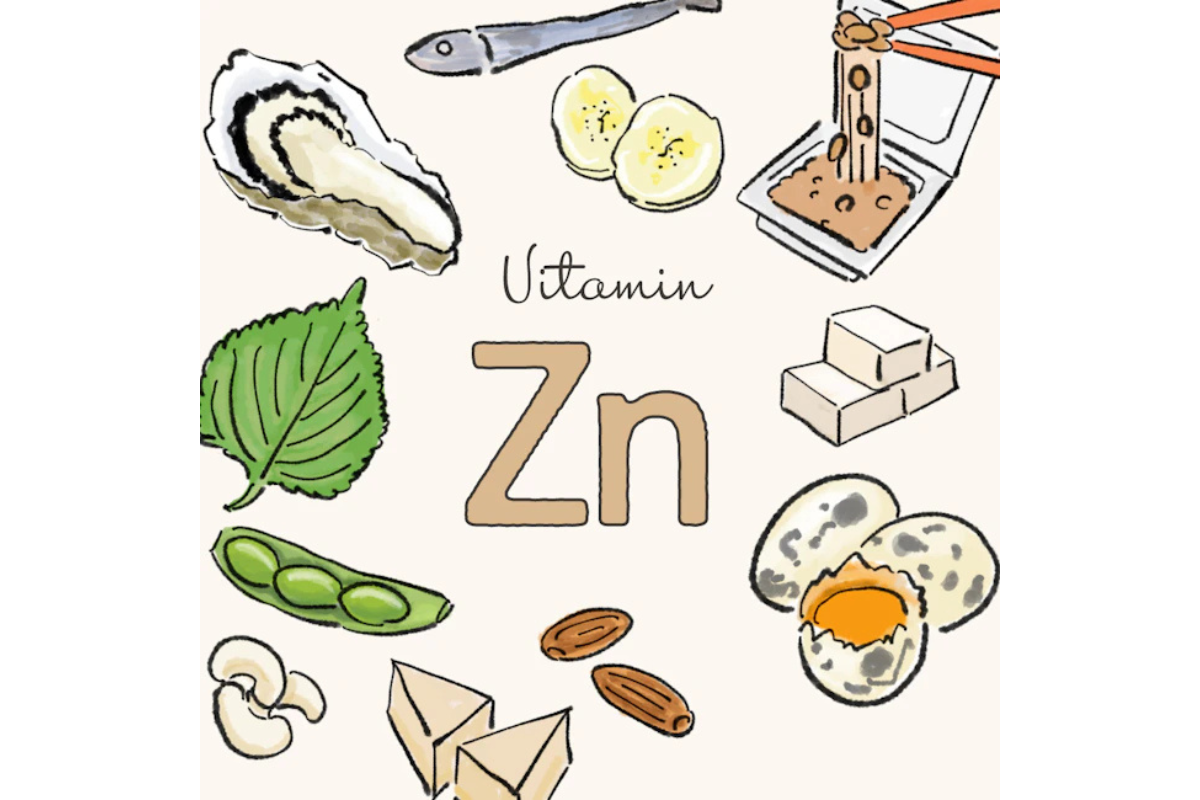

コメント